 お知らせ
お知らせ 提藍(ていらん)
提藍は、元々結婚式のお馳走を入れるもので、花婿が花嫁をお迎えに行くときにつかっていたものが多い。中国四川省、山東省などに多く、今、茶館で使っているものは、50年以上のアンティークものです。年数を得た趣が好きで、よく行く上海の骨董屋さんには、...
 お知らせ
お知らせ  お知らせ
お知らせ  お知らせ
お知らせ 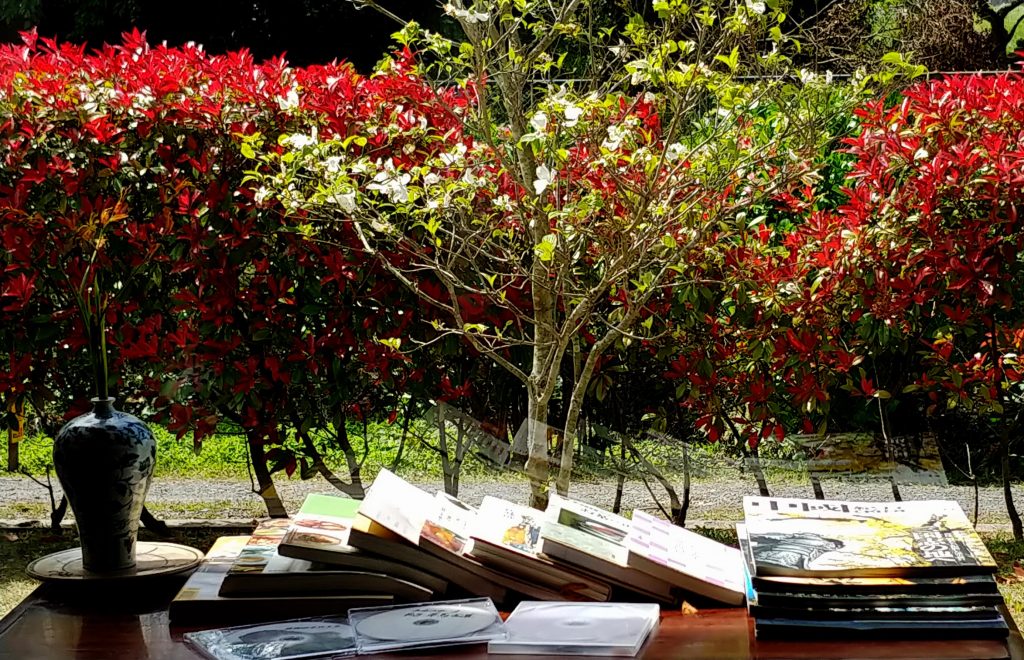 お知らせ
お知らせ  お知らせ
お知らせ  お知らせ
お知らせ  お知らせ
お知らせ  お知らせ
お知らせ  お知らせ
お知らせ 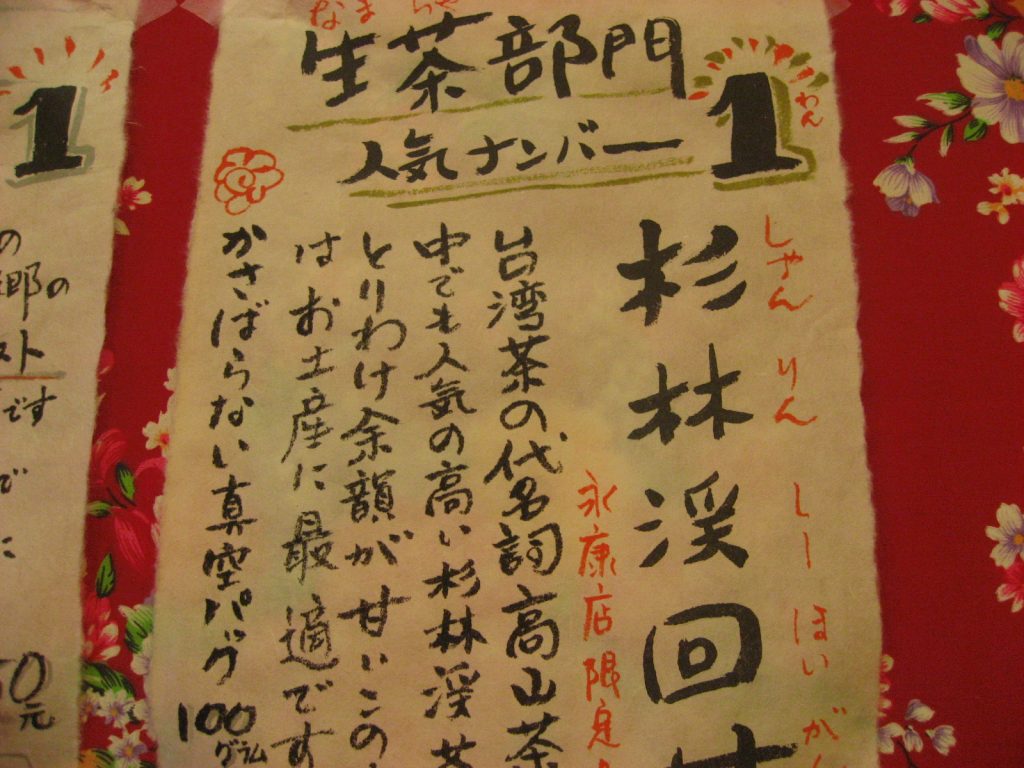 お知らせ
お知らせ